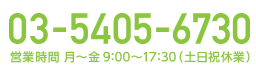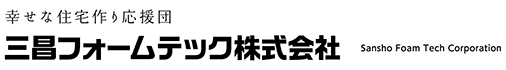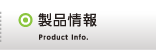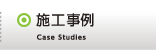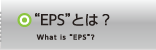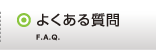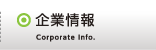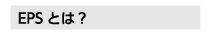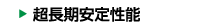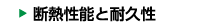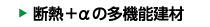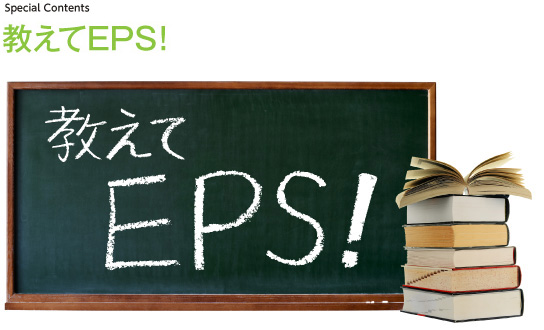突然ですが、ここでクイズです。
問題 『日本の現在の建築物の寿命はおおよそ何年でしょうか?』
答え 『39年』†1
「え~っ、たったの39年!?」と、驚きの声があちこちから聞こえてきそうですが、残念ながらこれが事実です。
木造建築や、鉄筋コンクリート構造など、工法によって実際の寿命は異なりますが、この『39年』には全てのRC造建築も含まれています。
寿命が短いとされるでは木造建築に限った場合の寿命は・・・? なんと、『30年』です。
「せっかく建てたマイホーム、それが30年しかもたないなんて・・・」と溜め息が出た方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もっと長く、マイホームと接していたい。そう感じるのが、マイホーム購入や、建て替えを検討される方の心情では無いかと感じます。
ここで比較として、海を渡った欧米では住宅の寿命はどうか見てみます。
以下、いくつかの国別に住宅平均寿命を列記します。
フランス→86年
ドイツ→87年
アメリカ→103年
イギリス→141年†2
日本に比べてずいぶんと長寿な事が伺えますね。
なぜこんなにも、日本の住宅の寿命は他の先進国と比べて短くなってしまっているのでしょうか?
まず文化的な違いが、その理由の一つで有ると考えられます。
日本文化の特異性として良く知られているのが、『「伝統を守ること」と「流行に敏感、変化を許容すること」、相反するように見えるこの二つを、器用に両立させている』事です。
歴史ある伝統的な建造物と、近代的な高層ビル郡。そしてその間を縫うように走る高架道路などの景観は、多くの海外からの観光客を驚かせ、SF映画の巨匠たちにインスピレーションを与えてきました。
伝統と最新の技術、その両方を柔軟に受け入れる独自の精神性が、ゲームやコミック、そして産業製品の開発といった近代日本の発展の礎であったと言うのは過言ではないかと思います。
この文化性は、諸説ありますが生活様式の中から生まれてきたと考えられます。
農耕民族として四季の移り変わりを楽しみつつ同時に、17世紀当時、既に世界最大規模のメガロポリスであった「江戸」の都市型生活を営んできた日本人は、近代化以前より流行、「旬」に敏感で有ることの楽しさ、最新の話題が駆け巡ることに慣れ親しんでいました。
それらを背景に、江戸では、200年以上続く「太平の世」として、豊かな大衆文化が花開く事になります。
そうしてトレンドに敏感となった日本人は、特に食事に関して「初物」好きで知られています。
新酒に新米、初ガツオや、そしてフランス人も不思議がったと言われる、日本の「ボジョレー・ヌーボー」ブーム。
「初物を食べると75日寿命が伸びる」という言葉も有るくらいですが、これだけ「新しい物好き」な日本人ですから、
住宅もまた「新築」が最も好まれるのも、当然のことかもしれません。
実際、今でも多くの方が「中古より新築」、「下町より新興住宅地」を好んでいる事は、各種統計を見るまでもなく明らかです。
さて、ここで話を欧米に戻します。
(後半へ続きます)
†1 出典:『大蔵省 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一」』
†2 出典:『建設省 「解体・リサイクル制度研究会報告―自立と連携によるリサイクル社会の構築と環境産業の創造を目指してー」 』 平成10年10月 解体・リサイクル制度研究会